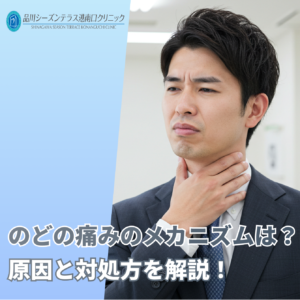高血圧とは?原因・症状・予防までわかりやすく解説
「高血圧」ってなに?高血圧とその原因とは
血圧が高い状態が続く“高血圧”とはどんな病気なのか、わかりやすく解説します。
高血圧とは、その名のとおり血圧が高い状態が長く続いていることを指します。血圧とは、血液が血管内を流れるときに血管の壁にかかる圧力のことです。一般的には、病院などの診察室での血圧が140/90mmHg以上、家庭で測定した血圧が135/85mmHg以上の場合に「高血圧」と診断されます。
高血圧は、原因がひとつではない「本態性(ほんたいせい)高血圧」と、原因が明らかな「二次性高血圧」に分類されます。日本人の高血圧の約8~9割が本態性高血圧と言われており、以下のようなさまざまな要因が組み合わさって起こります。
- 家族性の要因
家族に高血圧の人が多い家庭では、高血圧が起こりやすい傾向にあります。これは、遺伝的要因と、家族で似た生活環境(食塩摂取量が多い、過食や偏食による肥満が多い、運動不足など)になりがちという環境要因のどちらの可能性もあります。 - 食生活の乱れ
塩分の摂り過ぎは体内の水分量を増加させ、血圧が上がる要因となります。また、野菜や果物の不足(カリウムなどのミネラル不足)でナトリウムが十分排泄されなくなることも、血圧が上がる原因となります。また、過食や偏食などの結果生じる糖尿病や高脂血症、高尿酸血症(痛風)も、動脈硬化を進行させ血圧を上げる要因のひとつとなります。
- 運動不足・肥満
運動不足により血流が低下し、血管壁の弾力性が低下することで血圧が上がりやすくなります。また、運動不足や過食は肥満の原因となりますが、特に内臓脂肪型の肥満は血圧上昇と関係が深く要注意です。肥満は血管や心臓への過度の負担となります。 - 喫煙・過度な飲酒
タバコはまさしく『百害あって一利なし』です。喫煙は一時的に血管を収縮させて血圧を上げるだけでなく、常の血流そのものを悪くして血液が固まりやすくなり、動脈硬化の原因となります。
過度の飲酒は血圧上昇の一因となり、また中性脂肪を上昇させ動脈硬化を進行させます。従来、適量の飲酒はリラックス効果があり血圧を下げるとも言われていましたが、近年の研究では、高血圧に関しては男女とも少しの飲酒でも発症リスクが上昇するとの報告があります。 - ストレス・自律神経の乱れなど
過度なストレスは交感神経を刺激し、血管を収縮させて血圧を上昇させます。睡眠不足や便秘(によるいきみ)、その他、寒さや急激な気温差、自律神経の乱れなども血圧上昇の原因となります。
症状を自覚しにくいからこそ要注意!高血圧を放置するとどうなる?
軽く見過ごされがちな高血圧のサインを見逃さないために、代表的な症状を紹介します。
高血圧にははっきりとした特有の症状が少なく、健診などで指摘されたものの無症状で放置しているうちに高度な高血圧に進展してしまっているケースも珍しくありません。その一方で、次のようなサインが見られる場合があります。
- 朝起きたときの頭痛や重だるさ
朝は血圧が上がりやすく、起床時に頭痛や首すじの張りを感じることがあります。 - 肩こり・めまい
血圧の変動が大きいと、肩こりやふらつきを覚えることがあります。 - 耳鳴りや胸の圧迫感
血流の異常が起こることで、耳鳴りが続いたり胸がドキドキするような感覚を覚える人もいます。
これらの症状の原因が必ずしも高血圧であるとは限りませんが、高血圧を放置すると動脈硬化が進行し、心臓病(心筋梗塞・心不全など)や脳血管障害(脳梗塞・脳出血など)、また高血圧性の腎障害や眼障害を発症するリスクが高まります。重篤な疾患につながるリスクを減らすためにも、日常生活内での生活習慣改善や家庭血圧の測定とあわせて、早めに医療機関を受診し、診断や検査を受けることが大切です。
今日からできる!高血圧を防ぐ・改善するための生活習慣
食事・運動・ストレス管理まで、血圧をコントロールするための具体的な対策をお伝えします。

(1) 食事の見直し
- 塩分を控える
日本人は食塩を摂りすぎる傾向があります。ラーメン・うどんや漬物、味噌汁などは塩分が多いため、汁を全部飲まない・漬物を食べ過ぎないなど工夫が必要です。調味料を控えめにしたり、減塩のものを使用したりして、一日の塩分摂取量を6g未満(日本高血圧学会推奨)に近づけましょう。 - 野菜や果物、魚を増やす
カリウムを多く含む野菜や果物は、余分なナトリウムの排出を助け、血圧の上昇を抑える効果が期待できます。食事の際には、まず野菜やキノコ、海藻など食物繊維の多い食材から食べる「ベジファースト」を心がけ、塩分の過剰摂取を防ぐ工夫をすると良いでしょう。また、魚に含まれる油には高血圧を改善する効果があると言われています。 - バランスの良い食生活を意識
タンパク質、脂質、炭水化物をバランスよく摂りながら、過度なカロリー過多を避けることが大切です。肥満は高血圧の大きな要因の一つです。適正体重を維持するためにも暴飲暴食は控えましょう。
(2) 禁煙と適正飲酒
- 禁煙のためにできること
高血圧の予防・改善には、禁煙の取り組みが有効です。
まずは「吸いたくなるタイミング」を把握し、ガムや飴で気を紛らわせる・深呼吸で落ち着くといった代替行動を取り入れてみましょう。また、家族や友人にも協力をお願いし、禁煙を続けやすい環境を整えることも大切です。
ご自身の意思だけで禁煙することが難しい場合は、禁煙外来など医療機関のサポートをも活用してみましょう。 - 飲酒は「量と頻度の調整」がカギ
お酒を完全にやめる必要はありませんが、飲み方の見直しが血圧コントロールには重要です。
・毎日ではなく「週に2日は休肝日」を作る
・飲む量は「ビール中瓶1本、日本酒1合まで(男性の場合。女性はその半分~2/3程度)」を目安にする
・チェイサー(お水)を交えてゆっくり飲む
・塩分の多いおつまみや食べ過ぎを避ける
といった工夫で、血圧への影響をなるべく抑えましょう。
(3) 適度な運動
- 有酸素運動の習慣化
ウォーキングや軽いジョギング、サイクリング、水泳など、ゆっくりと続けられる有酸素運動が効果的です。毎日30分以上、または週180分以上の運動を継続することが推奨されています。 - 筋トレも適度に
無酸素運動でも、軽い負荷で回数をこなすような筋トレは血管を強くし、基礎代謝を上げるのに有効です。ただし、過度に息を止めるような重い負荷のトレーニングは血圧を急激に上げるリスクがあるので、既に高血圧をお持ちの方は要注意です。
(4) ストレス管理と十分な休養
- ストレスを溜め込まない
ストレスは自律神経のバランスを乱し、血圧を上昇させます。趣味やリラックスできる時間を確保し、日々のストレスを上手に発散する方法を見つけましょう。 - 十分な睡眠
睡眠不足は高血圧のリスクを高めます。質の良い睡眠を確保するために、寝る前のスマホやパソコンの使用を控え、ぬるめのお風呂に入る、照明を落とすなど、寝つきを良くする工夫をおすすめします。
高血圧に関するよくある質問に医師が答えます!
ここからは実際に診察室でよく聞かれる高血圧に関する質問にお答えしながら解説します。

Q1. 高血圧は治るの?
高血圧の原因や程度によっては、生活習慣の改善だけで血圧が正常値近くまで下がることがあります。ただし、一度高血圧と診断された方は、再び血圧が上がる可能性も高いため、継続的な管理が重要です。必要に応じて薬物療法を行いながら、食事・運動などの生活習慣の見直しを続けることで、安定した適正血圧を維持することが重要です。
Q2. 何歳から注意すればいい?
高血圧は中高年に多く見られる疾患ですが、近年は若年層でも食生活の乱れや運動不足などによって血圧が高くなるケースが増えています。そのため、若いうちから定期的に健康診断を受け、血圧を測定する習慣をつけることが大切です。20代・30代であっても家族に高血圧や心血管系の疾患がある場合には、より早い段階から注意しておくことをおすすめします。
Q3. アルコールは大丈夫?
適量のアルコールはリラックス効果が期待できる一方、過度な飲酒は血圧上昇の大きな要因となります。目安としては、男性の場合1日に日本酒なら1合(180mL)、ビールなら中ビン1本(500mL)、ワインならグラス2杯(240mL)ほどが適量です。女性の場合はその半分~3/4量が目安です。1回の飲酒量を適正化することに加えて、週に2日は休肝日(アルコールを飲まない日)を設けましょう。
Q4. タバコはいけない?
タバコは血管を収縮させて血圧を直接上げるだけでなく、動脈硬化や心疾患の高いリスク要因としても知られています。喫煙を続けるほど高血圧の管理は困難となり、脳卒中や心筋梗塞、大動脈瘤・大動脈解離などの重篤な疾患につながる危険性も高まります。禁煙は身体への負担を軽減し、高血圧改善にも大いに寄与します。健康的な生活習慣を維持するためにも、思い切ってタバコをやめることが長期的な血圧管理のカギとなります。紙タバコだけでなく、電子タバコも同様にリスク要因です。また、間接喫煙(受動喫煙)も大きなリスクとなります。
まとめ
高血圧は症状が乏しく見過ごされがちですが、放置すると心臓病や脳卒中など深刻な疾患につながる危険があります。塩分を控えた食事や適度な運動、十分な睡眠、ストレスの軽減は血圧の安定に役立ちます。
また、喫煙や過度の飲酒も血圧を大きく上昇させる原因となるため要注意です。若い世代でも生活習慣の乱れから高血圧を発症するケースが増えており、異変を感じたら早めに医療機関で相談し、日々の血圧測定や必要に応じた薬物療法を導入することが大切です。
品川シーズンテラス港南口クリニックではのどの痛みをはじめ、風邪や発熱、胃腸炎、花粉症やその他生活習慣病などにも対応しております。レントゲン、心電図、超音波画像診断装置等を備えており、必要に応じた検査を行いながら患者さまの健康をサポートしています。気になる症状がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
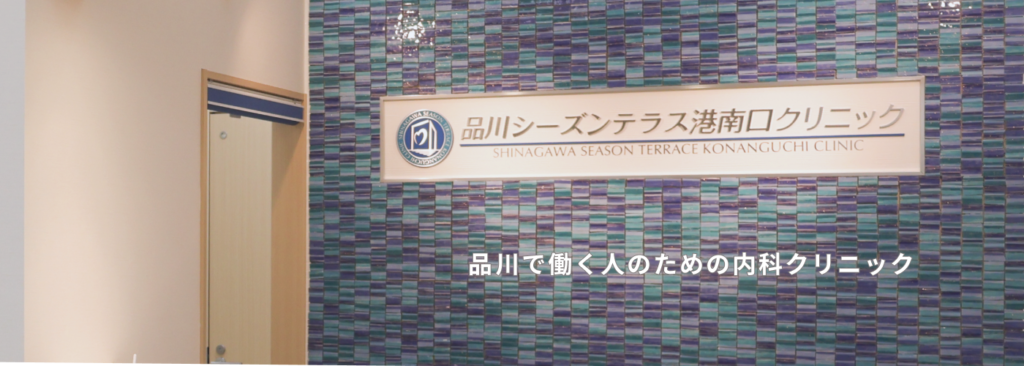
参考資料
監修医師

院長:濱本 貴子
徳島大学医学部卒業後、心臓血管外科・循環器科などで経験を積み、2015年に港区にて開業。高血圧・糖尿病・高脂血症・痛風といった生活習慣病をはじめ、風邪や胃腸炎、花粉症など、日常的な内科診療に幅広く対応している